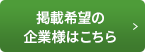【完全網羅】遺品整理で『絶対に』捨ててはいけないもの16選!注意点もあわせて解説
2024.01.10

- 遺品整理をする前に『これだけは絶対に捨ててはいけないもの』を知っておきたい
- その際に気をつけた方がいいことも知りたい
- 間違えて捨てないための対策方法はあるの?
こんな悩みにお答えします。
遺品整理をはじめようにも、「もし必要なものを捨ててしまったらどうしよう…」と考えたことはありませんか?
捨ててはいけないものを処分すると、相続トラブルなど親族間でもめる原因になることも。
この記事では、
- 絶対に捨ててはいけないもの16選とそれぞれの注意点
- 捨ててはいけないものを処分してしまったら起こるトラブル
- 捨ててはいけない遺品を守る7つの対策
について解説しますので、捨ててはいけないものを網羅的に把握でき、後々のトラブルを事前にガッチリ防げるようになりますよ。
遺品整理をこれからはじめる方や、トラブルなく遺品整理を進めたい方はぜひ最後まで読んでみてください。
【完全網羅】遺品整理で『絶対に』捨ててはいけないもの16選!注意点もあわせて解説
あらかじめ捨ててはいけないものを把握できれば、
- 親族間のトラブルを防げる
- 後悔を避けられる
- 遺品整理をスムーズに進められる
など、多くのメリットがあります。
16項目に分けてリストにしましたので、事前にチェックしておきましょう。
| 絶対に捨ててはいけないもの | |
|---|---|
| 遺言書 | 現金 |
| 有価証券・保険証券 | ローンの明細 |
| 土地・不動産などの権利関係書類 | 通帳 |
| 印鑑 | 身分証明書 |
| 年金手帳 | 仕事に関する書類 |
| レンタル品 | デジタル遺品 |
| 鍵 | 価値のあるもの |
| 故人宛の手紙や郵便物 | 思い出の品 |
では、順番に注意点とあわせて解説します。
遺言書
遺言書は法的な拘束力があり、遺品の相続に必要な書類です。
故人の意思を確認できますので、後々のトラブルを防ぐためにも絶対に捨ててはいけません。
遺言書の種類は以下のとおりです。
| 遺言書の種類 | 作成方法 | 証人 | 保管方法 | 検認手続き |
|---|---|---|---|---|
|
自筆証書遺言 |
自分で遺言書を書き、押印する |
不要 |
被相続人が保管 |
必要 |
|
公正証書遺言 |
公証役場にて被相続人が遺言内容を話し、それを公証人が記述する |
必要 |
公証役場で保管 |
不要 |
|
秘密証書遺言 |
署名・押印した遺言書を封筒に入れて封印し、公証役場で証明してもらう |
必要 |
被相続人が保管 |
必要 |
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、どこかに収納したり、誰かに預けたりしています。
探しても見つからない場合は、
- 法務局の遺言書保管所
- 公証役場の遺言検索システム
- 生前に交流があった人への確認
などの方法で探してみましょう。
【注意点】意図的に破棄するとペナルティの対象になる
遺言書を意図的に捨てた場合は、相続欠格になります。
相続欠格とは、相続人が相続に関する法律を犯すようなことをしたときに、相続人としての資格を失うことを指します。
「私用文書等毀棄罪」が成立すると、5年以下の懲役刑に処される可能性もあります。
ただし、うっかり捨てた場合は、ペナルティはありませんのでご安心を。
公正証書遺言であれば再発行してもらえますが、捨てないように細心の注意を払いましょう。
現金
遺品整理で見つかった現金は、すべて残しておきましょう。
相続財産として相続の対象になるからです。
以下のような場所に隠されているケースがありますので、袋や封筒などを破棄するときはこまめに中身をチェックしましょう。
- タンス
- 金庫
- お菓子の缶
- 本の中
- ファイル
- ポーチ
たとえば、台所にいる時間が長い方は、手っ取り早く食器棚の引き出しに印鑑や通帳とともに現金を置いていることはよくあります。
なお、解除するのにカード番号などが必要ですので、出てきたクレジットカードも保管しておきましょう。
【注意点】遺産分割協議が終わるまで使ってはいけない
出てきた現金や預貯金などを無断で使うと、着服を疑われてしまいます。
親族間のトラブルを避けるためにも、遺産分割が終わるまで現金には手をつけないようにしましょう。
有価証券・保険証券
資産を把握するうえで必要ですし、遺産分割の対象になりますので捨てないようにしましょう。
有価証券とは
- 株式
- 債券
- 小切手
- 手形
などを指し、保険証券とは保険契約が成立したあとに保険会社から交付される契約内容が書かれた文書を指します。
いずれも重要な書類ですので、残しておきましょう。
【注意点】捨てると手間がかかる
捨ててしまうと申告や手続きが必要になり、手間と時間がかかります。
証券会社や保険会社への問い合わせに追われますので、捨てないようにご注意ください。
ローンの明細
相続ではマイナスの財産も引き継ぐ対象になりますので、ローンの明細は捨てないようにしましょう。
プラスの相続財産よりもローンの返済残高が多い場合などは、相続放棄ができるからです。
ローン残高の詳細は、ローン会社へ問い合わせをしてきちんと把握し、明細はきちんと保管しておきましょう。
【注意点】相続放棄の期限に気をつけよう
相続放棄する場合は、相続開始の事実を知った日から3ヶ月以内に届出が必要です。
できるだけ早い段階でローンの存在や金額を把握し、相続放棄するかを検討し、期限を逃さないようにご注意ください。
土地・不動産などの権利関係書類
権利関係書類があれば、土地・不動産についての話し合いをスムーズにできます。
たとえば、土地の上に建物が立っているシンプルなパターンもあれば、私道や駐車場の持分を所有しているパターンもありますので、ややこしい状況こそ権利関係書類が役に立つからです。
【注意点】捨ててしまっても慌てなくて大丈夫
もし捨ててしまっても、相続登記をして土地の所有権は変更できます。
現在の所有者がすでに他界していると意思確認はできませんし、戸籍謄本などで登記の原因が相続によるものだと証明できるからです。
権利関係書類を捨ててしまっても、慌てず対処しましょう。
通帳
相続手続きをしている凍結口座の解除には、通帳やキャッシュカードが必要です。
たとえ親族でも故人の現金を引き出すのが困難になってしまいます。
通帳があれば、
- お金の流れ
- 取引の内容
- ローンなど借り入れの状況
- 保険の払込状況
などを確認できますので、すぐにストップすべき取引にも対処できます。
【注意点】凍結前の口座は触ってはいけない
口座凍結されるまえに預金を引き出すと、相続財産の金額がわからなくなり、相続放棄に支障をきたします。
また、相続税の課税対象ですので脱税行為にもなってしまいます。
親族間のトラブルを避けるためにも、口座名義人が亡くなったときはすみやかに銀行に届け出をしましょう。
印鑑
故人の印鑑を捨ててしまうと、解約・解除の手続きが進められなくなりますので、気をつけましょう。
たとえば、印鑑証明に使用した印鑑を捨ててしまうと、以下のような手続きが大変になります。
- 印鑑登録の手続きの廃止
- 戸籍謄本の取得
- 凍結された口座の解除
さまざまな場面で使われている、
- 実印
- 銀行印
- 認印
- 訂正印
などは捨てないようにし、スムーズに死後の手続きを進めるためにも保管しておきましょう。
【注意点】故人が経営者の場合は法人用の印鑑も保管しておく
故人が経営者だった場合は、会社に関する印鑑にも気を配りましょう。
後々の手続きで必要になりますので、
- 会社実印
- 会社銀行印
- 会社角印
は捨てないようにし、保管しておきましょう。
身分証明書
以下のような証明書も残しておきましょう。
- 運転免許証
- 健康保険証
- 高齢受給者証
- 介護保険被保険者証
- 障害者手帳
- 被保険者証
- マイナンバーカード
- パスポート
身分証明書を捨ててはいけない理由は、次のとおりです。
- 死亡届出後の役所での手続きで必要だから
- 返還しなければいけない証明書があるから
- 故人が利用していたサービスの解約手続きで必要なケースがあるから
運転免許証は必ずしも返還する必要はありませんが、ほとんどの身分証明書は返還する必要がありますので、捨てないようにしましょう。
【注意点】サブスクリプション契約を確認する
身分証明書はサブスク契約を解除するときに必要になる場合があります。
捨ててしまって解約に時間がかかると、サービス料金もかかり続けてしまう恐れがありますので、忘れずに以下のようなサービスを解約・解除しましょう。
- Netflixなどの動画配信サービス
- Spotifyなどの音楽配信サービス
- 野菜やコーヒーなどの定期便
- ファンクラブなどの会員契約 など
あげるとキリがないほど多くのサブスク契約が存在しますので、注意深くチェックしておきましょう。
年金手帳
捨ててしまうと故人が年金受給者かどうかを証明しにくくなります。
故人が年金受給者の場合は「年金受給権者死亡届」と一緒に提出し、受給停止の手続きをする必要がありますので年金手帳は残しておきましょう。
厚生年金と共済年金は死後10日以内、国民年金は死後14日以内に「年金事務所」もしくは「年金相談センター」に届出を出して手続きをします。
【注意点】届出が遅れると返金の対象になる
年金手帳を捨ててしまうと、死後に受け取った年金の払い戻しをする手間が発生します。
いつまでも手続きをしないで、故人の口座に年金が振り込み続けられていると、最悪のケースとして詐欺罪に問われることもありますのでご注意ください。
仕事に関する書類
紙媒体だけでなく、パソコン内の電子ファイルなども残しておきましょう。
故人の仕事内容の引き継ぎや、会社の業務にとって必要なケースがあるからです。
親族以外にも迷惑をかけてしまうことにご留意ください。
【注意点】安易に自分たちで判断してはいけない
仕事関係の書類は捨てるまえに、会社側にこまめに確認しましょう。
勝手に捨てるとトラブルの原因になり、損害賠償リスクも高まります。故人が経営者の場合は、法人の手続きに必要な書類も含まれますのでご注意ください。
レンタル品
レンタル品やリース品は借りていることに気づかずに捨ててしまうケースがあります。
捨ててしまうと、以下のようなリスクに見舞われます。
- 弁償
- 延滞料金
- 損害賠償
一例になりますが、
- CD・DVD
- 本
- Wi-Fiルーター・モデム
- テレビを見るための衛生やチューナー
- 車
- ウォーターサーバー
- 介護用のベッドや手すり
などのレンタル品は、間違えて捨てないように注意深く確認しましょう。
【注意点】見分けがつきにくいレンタル品とは
近年はレンタルサービスの種類も豊富になり、以下のレンタル品は見分けがつきにくいのでご注意ください。
- 洋服
- 家具
- 家電
図書館から貸し出された本なども、うっかり捨ててしまわないように気をつけましょう。
デジタル遺品
デジタル遺品とは故人が登録したインターネット上の登録情報を指し、次のようなものが該当します。
- パソコンやスマホ内の保存データ
- メールやSNSのアカウント
- 金融機関の取引アカウント
- ネットバンキングの情報
- サブスクリプションの情報
捨てたり消去したりすると手間や時間がかかり、
- 相続トラブル
- SNSなどへの不正アクセス
- 個人情報の流出
- 月額費用の継続
などのトラブルに発展する可能性がありますので、安易に捨てたり初期化したりせずに、データを残しておきましょう。
【注意点】デジタル遺品には隠れた負債があることも
デジタル遺品は捨てるどころか、早期に発見して中身を把握しましょう。
隠れた負債の存在に気づかずに、相続してしまうトラブルも発生していますのでご注意ください。

鍵
うっかり鍵を捨ててしまわないようにしましょう。
荷物をすぐに取り出せなくなったり、鍵の交換費用や手間がかかったりします。
- 家
- 倉庫
- ロッカー
- 机の引き出し
- 車
- バイク
などの鍵は不要になるまではきちんと管理しておきましょう。
【注意点】鍵にはいろんな形がある
よくある鍵の形にとらわれず、カード式の鍵があることもお忘れなく。
また、「これは一体何の鍵?」という鍵が出てきたら、鍵屋に相談しましょう。
鍵の形状やナンバーから、何の鍵かわかる可能性がありますので、見つけた鍵はしばらく保管しておきましょう。
価値のあるもの
価値のあるものは相続財産になりますので、うっかり捨ててしまうと予想外の損失や相続トラブルにつながることも。
「実は高価な遺品だった…」とならないように、価値のありそうな以下の遺品は慎重に判断しましょう。
- 美術品
- 骨董品
- 貴金属
- フィギュア
- ブランド品
- 着物
- 代々先祖から受け継いできたもの
捨ててしまわないためにも、親族間でしっかり確認してから処分することをおすすめします。
【注意点】コレクションの扱いには気をつけよう
興味のない人からするとガラクタに思えるようなものでも、コレクターからすると喉から手が出るほど欲しいものは世の中にたくさんあります。
- 切手
- 古銭
- 昔のおもちゃ
- プラモデル
- フィギュア
- レコード など
限定品・記念品や数量に限りのある希少性の高いもの、販売終了したものなどは高額で売れることもありますので、捨ててしまわないように気をつけましょう。

故人宛の手紙や郵便物
手紙や郵便物は故人が築いた人間関係を辿れる、貴重な情報源になります。
故人が亡くなったときは、ひとりでも多くの方に訃報を入れることで、遺品整理するうえで気をつけるべきポイントなどの情報を掴める可能性もあります。
【注意点】重要書類には気をつけよう
次のような大切な書類が含まれていることがあります。
- 公的機関からのお知らせ
- 保険金の支払い通知
- 年金の支払いに関する通知
- 未払いの税金の通知
- 光熱費の請求やお知らせ通知
しかるべき手続きをとってから捨てるようにしましょう。
思い出の品
思い出の品を扱うときは気をつけましょう。
捨ててしまうと取り返しがつきませんし、精神的なショックも大きくなるからです。
とはいえ、「残しすぎると遺品整理がなかなか進まないよ」という意見もあるでしょう。
そんなときは写真を撮ったり動画にしたり、データとして保存することをおすすめします。
【注意点】思い出の品はひとりで判断しない
自分にとってはたいしたことがなくても、家族にとっては思い入れのある遺品もあります。
トラブルを防止するためにも、ひとりで判断せずに、事前に家族などに相談して捨ててしまわないように対策しましょう。
遺品整理で捨ててはいけないものを処分するリスクとは?
捨ててはいけないものを処分すると、以下のようなリスクが伴います。
- 親族間でのトラブル
- 相続税の申告漏れ
- 損害賠償
最悪のケースを想定するためにも、参考にしてみてください。
親族間でのトラブル
捨ててはいけないものを処分すると、親族間でのトラブルへ発展し、遺品整理や遺産分割が進まなくなるリスクが高まります。
たとえば、相続税申告時に未分割という状況になり、不動産の売却などができなくなるケースもあります。
相続税の申告漏れ
捨ててはいけないものを処分すると、相続税の申告漏れにつながる恐れがあります。
相続税は死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりませんので、申告が漏れると以下のような税金が余分にかかってしまいます。
- 無申告加算税(通常の税金の5~20%増)
- 過少申告加算税(通常の税金の10~15%増)
本来よりも多くの税金を支払う羽目にならないように気をつけましょう。
損害賠償
レンタル品やリース品は他人の財物なので、捨ててしまうと損害賠償請求されるリスクがあります。
もちろん遺族が負担することになりますが、約款次第では適用される可能性がありますので賠償責任保険への加入を確認してみてください。
火災保険の特約としてセットされているケースもありますので、加入していれば保障されるのかを保険会社に相談してみましょう。
捨ててはいけない遺品を守る7つの対策
大切な遺品を捨ててしまわないために、次の7つの対策を行いましょう。
- 【対策①】生前に話し合う
- 【対策②】遺言書を確認する
- 【対策③】エンディングノートを確認する
- 【対策④】複数人で作業する
- 【対策⑤】段階的に整理する
- 【対策⑥】遺品整理士の力を借りる
- 【対策⑦】判断に迷うものは残す
【対策①】生前に話し合う
生前に話し合う機会があれば、遺品整理で「捨てていいもの」「捨ててはいけないもの」の基準が明確になります。
故人の意思を的確に反映できますし、親族同士の目線合わせもできます。
「捨てていいもの」「捨ててはいけないもの」をリスト化し、
- 大切な遺品の保管場所
- 各種ID・パスワード
- 契約しているサービス類
なども忘れずにチェックしておきましょう。
後々のリスクヘッジにつながりますので、生前の話し合いは効果的な対策です。
【対策②】遺言書を確認する
遺品整理では、第一優先で遺言書を確認しましょう。
法的にも重要な書類であり、故人の意思が反映されているからです。
- 遺品を誰に譲るのか
- 遺品をどうやって処分するのか
- 相続をどのようにするのか
などの情報をもとに、遺品整理で捨ててはいけないものを判断しましょう。
【対策③】エンディングノートを確認する
捨ててはいけないもを知るうえで重要な手がかりになります。
亡くなる前に死後のことを想定して、次のような遺品整理で必要な情報をまとめているからです。
- 自分のこと
- 遺言書の有無
- 財産や資産
- 家族や友人、ペットについて
- 身の回りのこと
- 葬儀やお墓について
- ID・パスワード
- 契約しているサービス
故人が遺族にしっかり意思表示できる一方で、遺言書とは異なり法的拘束力はありませんので、故人の意思が100%叶うわけではない点にご留意ください。
【対策④】複数人で作業する
相談しながら遺品整理ができますので、ひとりで判断するよりも、捨ててはいけないものを守れる確率が上がります。
判断に迷うものは複数人で作業ができる日にとっておくなど、なるべく相談できる環境で遺品整理を行いましょう。
【対策⑤】段階的に整理する
「早く遺品整理を終わらせたい」という気持ちもあるかもしれません。
しかし、急ぐと捨ててはいけないものまで処分するなど、ミスの原因になりかねません。
特に相続税の申告に関係がない遺品は時間をかけても問題ありませんので、
- 葬儀後
- 諸手続きが終わった後
- 四十九日を迎えた後
- 相続税の発生前
- 親族が集まるとき
などのタイミングで段階的に遺品整理を進めましょう。
【対策⑥】遺品整理士の力を借りる
経験豊富なプロの力を借りましょう。
遺品整理士に依頼すると、
- 法的に捨ててはいけないものを熟知している
- 捨ててはいけない遺品の在処を突き止めることに長けている
- 遺品を適切に整理してくれる
- 今後の手続きや遺品の保管についてアドバイスがもらえる
などの多くのメリットがあります。
専門家のアドバイスを参考に、捨ててはいけないものをガッチリ守りましょう。
【対策⑦】判断に迷うものは残す
「これ捨ててもいいかな?」と迷ったら、とりあえず残しましょう。
もちろん残し過ぎには注意が必要ですが、「やってしまった…」という後悔を避けられます。
迷ったものはダンボールなどに入れて分け、日を改めて段階的に処分しましょう。
「捨ててしまったらどうしよう」という不安が拭えない場合
「ミスしたらどうしよう」
「親族間でのトラブルは避けたい」
という不安が拭えないときは、遺品整理業者への依頼を検討しましょう。
理由は以下のとおりです。
- 経験が豊富で、適切なアドバイスが受けられるから
- スムーズに遺品整理ができるから
- 捨ててはいけないものを守れるから
経験に勝るものはありません。
数々の作業現場で培った経験より、通帳や印鑑、へそくりなどの置き場所の見当がつきやすく、間違えて捨ててしまう前に対策できるでしょう。
もちろん費用はかかりますが、プロの知識と経験をフル活用すれば、確実に捨ててはいけないものを守れるでしょう。
事前に捨ててはいけないものを把握して、トラブルのない遺品整理を!
今回は遺品整理で『絶対に』捨ててはいけないもの16選について解説しました。
| 絶対に捨ててはいけないもの | |
|---|---|
| 遺言書 | 現金 |
| 有価証券・保険証券 | ローンの明細 |
| 土地・不動産などの権利関係書類 | 通帳 |
| 印鑑 | 身分証明書 |
| 年金手帳 | 仕事に関する書類 |
| レンタル品 | デジタル遺品 |
| 鍵 | 価値のあるもの |
| 故人宛の手紙や郵便物 | 思い出の品 |
本記事をまとめると、
①捨ててはいけないものを把握しておけば、以下のトラブルを回避できる
- 親族間でのトラブル
- 相続税の申告漏れ
- 損害賠償
②7つの対策をしておけば、遺品整理で捨ててはいけないものを守れる
- 【対策①】生前に話し合う
- 【対策②】遺言書を確認する
- 【対策③】エンディングノートを確認する
- 【対策④】複数人で作業する
- 【対策⑤】段階的に整理する
- 【対策⑥】遺品整理士の力を借りる
- 【対策⑦】判断に迷うものは残す
③石橋を叩いて渡るには、遺品整理業者への依頼を検討しよう
親族でなかなか集まれなかったり、仕事や家事が忙しく遺品整理に時間をかけれなかったりするほど、捨ててはいけないものを処分してしまうリスクが高まります。
本記事を参考に、後悔しないためにも事前に対策してくださいね。