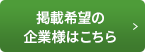形見分けではお返しがいらない3つの理由とは?マナーやお礼の仕方について徹底解説
2025.05.15

- 形見分けってなに?お返しは必要なの?
- 形見分けでお返しがいらない理由を知りたい
- 形見分けでのマナーやお礼の方法を知りたい
こんな悩みにお答えします。
形見分けとは、遺族が故人の遺品を大切な人たちへ分ける行為です。しかし、形見分けには特有の作法や、お返しがいらない理由があるため、戸惑う方も多いでしょう。
そこで、この記事では以下の内容をお伝えします。
- 形見分けの基本的な意味や目的、タイミング
- 形見分けではお返しがいらない3つの理由
- もらう側における形見分けのマナーとポイント
- 形見分けに対してお礼を伝える4つの方法
- 形見が不要になった場合の3つの対処法
形見を受け取った方や、これから形見を受け取る予定の方にとって、知っておきたい内容をまとめました。
形見分けについて知ることで、正しいマナーを実践しながら、感謝の気持ちを伝えることができます。最後までチェックし、悩まずに形見分けに向き合える準備を整えましょう!
形見分けの基本を押さえておこう!
形見分けとは、故人の遺品を友人や親しい人々に分配し、故人を供養するための大切な儀式です。
形見分けは一般的に法要が終わった後や忌明けのタイミングで行われ、故人が愛用していた品物を受け取ることで、その人への絆を感じ、感謝の気持ちを遺族と分かち合えます。
このような大切な儀式では、適切なマナーを守ることが不可欠です。形見分けの目的や流れを正しく理解し、心を込めて供養しましょう。
ここでは形見分けの基本について、くわしく解説します。
形見分けの意味とは?
形見分けとは、故人が生前に大切にしていた品々を、遺族が故人と親しくしていた友人や知人に贈ることで、故人を偲び、供養の意を込めた行為です。
この行為を通じて、遺族や知人が故人との思い出を共有し、故人の生きた証を心に刻み、その存在を大切に受け継いでいくことができます。また、形見分けには、単なる品物の受け渡し以上に、故人の意思や想いをつなぐという重要な役割があります。
特に、遺言がある場合はその内容に基づいて分けられることがありますが、多くの場合は遺族が慎重に故人の意志を考慮して品物を選びます。
このように、形見分けを行うことは、故人への供養となると共に、残された者がその思いに向き合い、絆を深める大切な機会となります。
形見分けを行う理由とは?
形見分けを行う理由は、遺族が故人の思い出を共有し、その供養を通じて心の整理をするためです。
故人との親しい関係を持つ人々に、その方が生前に大切にしていた品物を贈ることで、思い出を懐かしみ、一緒に故人を偲ぶ時間を持つことができます。また、形見分けは遺族にとって、悲しみを癒し、新たな一歩を踏み出す手段でもあります。
受け取る側は、形見を手にすることで、心の中に故人が生き続けていることを実感し、それぞれが故人への感謝や思いを改めて深める機会となるでしょう。
同時に、形見分けは遺産分割の一環としても重要な役割を果たします。形見分けを通じて、品物それぞれの価値以上の故人の込められた思いを受け取りながら、円滑に遺産を分配するプロセスの一部ともなります。
そうした行為を通じ、多くの感慨を分かち合いながら、故人の供養となる時間を共有することができるでしょう。
形見分けを行うタイミングとは?
形見分けのタイミングは、一般的に忌明けの法要を終えた後とされています。
仏式では四十九日法要を区切りとし、神道では30日祭もしくは50日祭を区切りとして形見分けが行われます。また、キリスト教では30日目の追悼ミサが目安となることが多いです。
このような法要の後、遺族が自宅に集まり形見分けを行うことが一般的ですが、場合によっては友人や親しい知人が招かれることもあります。
形見分けの時期は、故人の遺志や遺族それぞれの生活状況によって異なる場合がありますが、大切なのは心の整理をつけた上で行うことです。特に遺族が落ち着いた状態で形見分けを進めることが、スムーズな進行と良好な人間関係を保つために重要です。
また、故人の大切な品を受け取る側もその意義を理解し、故人を思い出しながら大切に扱うことが望まれます。
基本的に形見分けでは『お返し』しなくていい
形見分けの際に受け取った側が『お返し』をする必要は基本的にありません。
形見分けは、故人の遺族が遺品を通じて故人を偲んでもらうための行為であり、その際に返礼の品を用意する必要はないとされているからです。
この慣習は、形見分けが遺族からの心遣いであることを示しており、受け取る側はその気持ちに感謝しつつ、故人との関係を大切にする姿勢が求められます。
ただし、お返しはしなくていいのであって、してはいけないものではありません。後述しますが、場合によっては手紙を送ったり、電話で感謝の気持ちを丁寧に伝えるのも良い手段となります。大切なのは、形式的なお返しよりも相手の心に寄り添い、感謝や心を込めた対応を重視することです。
お返しは必須ではないことを押さえておきましょう。

形見分けではお返しがいらない3つの理由
形見分けではお返しは必須ではありません。
なぜなら、以下の3つの理由があるからです。
- 形見はお祝いの品やプレゼントではないから
- そもそも遺族は求めていないから
- お返しが慣習となっていないから
大切なのは、形見分けはお礼として何かを返すのではなく、故人を想い、つながりを感じながらその記憶を受け継ぐための行為と捉えること。
では、それぞれの理由について確認していきましょう。
①形見はお祝いの品やプレゼントではないから
形見分けにおいて贈られる品物は、日常的なお祝いの品やプレゼントとは異なる特別な意味を持っているからです。
それらの品物は、故人が生前に大切に使用し、愛着を持っていたものであり、故人の思い出や精神を受け継ぐ目的で手渡されます。形見分けは感謝や思い出を共有し、故人を供養する一環として行われるのです。
そのため、形見分けで受け取った品物に対してお返しはしなくて良いとされています。通常の場合、感謝の気持ちを丁寧に伝えるだけで十分です。
②そもそも遺族は求めていないから
そもそも形見分けを行う遺族にとって、受け取る側からのお返しは基本的に求めていないのが一般的です。
遺族が遺品を贈る際の意図は、故人を偲んでもらい、思い出を受け継いでほしいという気持ちにあります。
そのため、形見分けの際に過剰なお返しをすることは「いらない」と考える遺族も多く、むしろ互いに故人の思い出を大切にすることを重要視します。
お返しに捉われず穏やかな気持ちで受け入れることが、形見分けを円滑に行うためのマナーとしても適切なのです。
③お返しが慣習となっていないから
形見分けにおいてお返しをすることが慣習ではないため、特別な理由がない限り、お返しが求められることはありません。
日本の文化や慣習において、形見分けは故人の遺族から心を込めて贈られる大切な贈り物として位置づけられています。
そのため、贈られる側としては感謝の気持ちで受け取ることが期待され、形式的なお返しは「いらない」とされています。
このような文化的背景から、形見分けにおけるお返しは慣習として定着すらしていないのです。
【もらう側】形見分けのマナーとポイント
形見分けを受ける際のマナーとポイントについて押さえておきましょう。
まず、親しい関係であった故人の品物をもらうことは、感謝の気持ちを持ちながら受けることが重要です。しかし、もしその品物が生活に合わない場合や、自分にとって必要ないと感じる場合は、断ってもかまいません。
また、形見として受け取る品物が金銭的価値がある場合には、相続税や贈与税が課税されることも念頭におきましょう。
形見分けは故人の思いを共有する大切な機会ですが、自分自身の気持ちも大切にしつつ、思わぬ税負担のリスクも視野に入れておきましょう。
形見分けは断ってもいい
形見分けの際、形見が自分にとって不要だと感じることもあるでしょう。
そんなときは遺族からの申し出を無理に受け入れる必要はありません。受け取る側が何らかの理由で形見分けを断ることも、マナーとして認められています。特に、個人的な事情や心理的な負担を感じる場合には、無理をして受け取る必要はありません。
このような場合の断り方としては、大切なお気持ちはありがたく受け取ったうえで、自分の事情を簡潔に説明し、誠意を持って断りの意を伝えることが大切です。
こうすることで、遺族との関係性を損なうことなく、故人を思う気持ちを尊重する姿勢を示せます。無理をすることなく、自分の気持ちを正直に伝えることで、双方にとって安心感のある選択肢となるでしょう。
相続税や贈与税に注意する
形見分けされる品物が高価な場合や、現金が大きな金額だった場合は、相続税や贈与税が課される可能性があるため注意が必要です。
受け取った品物が遺族の相続財産と見なされると、相続税や贈与税が発生するケースがあります。このため、遺品の価値を事前に正確に把握し、税金がかかる場合は忘れずに適切な手続きを行いましょう。
税金に関する不明点がある場合や複雑な手続きが必要な場合には、専門の税理士事務所や行政の相談窓口に問い合わせることで、具体的で適切なアドバイスを受けることができます。
形見分けを受ける際は、形見が効果な場合は課税される恐れがあることを念頭に、慎重に受け取るようにしましょう。

形見分けに対してお礼を伝える5つの方法
とはいえ、「形見分けに対して感謝の気持ちをきちんと伝えたい!」という方もいるかと思います。
形見分けではお返しはしてはいけないというルールはないため、お返しをする際は以下の5つの方法を検討してみてください。
- お礼の手紙を書く
- 電話で感謝の気持ちを伝える
- 遺族と故人との思い出を分かち合う
- 法事に参加する
- カタログギフトを贈る
心を込めてこれらの方法を実践することで、形見分けをいただいたことへの深い感謝の意をしっかりと伝えられるでしょう。
それぞれの方法を深掘りして解説していきます。
①お礼の手紙を書く
形見分けを受け取った際には、お礼状や手紙で感謝を伝える方法があります。
お礼状や手紙には形見分けの品物に対する感想や思い出、さらには故人との心に残るエピソードを交えることで、より深みと温かみが感じられる内容に仕上がります。
また、手書きの文字には感謝の気持ちや真心が伝わりやすく、遺族とのつながりをより深める効果的な手段となります。
心を込めた礼状を作成し、あなたの思いを綴ってみてはいかがでしょうか。

②電話で感謝の気持ちを伝える
形見分けに対するお礼を電話で伝えることは、一つの効果的な手段です。
直接声を聞くことで、感謝の気持ちがより一層伝わりやすくなるからです。
時間が取れる場合は、電話をかけて感謝の言葉を伝えるだけでなく、故人との思い出を共有しながら話を進めると良いでしょう。
その際、遺族の感情に配慮しつつ、温かい思い出を交えた会話を心がけることで、互いの心のつながりをより深めることができます。
③遺族と故人との思い出を分かち合う
形見分けの品を受け取った際には、遺族と故人との思い出を分かち合うことも感謝の表現の一つです。
思い出を語ることで、お互いに故人を偲ぶことができ、心の距離が縮まります。特に故人との特別なエピソードや、共有していた経験を話すことで、感情の絆が生まれ、共感が生じることも多いです。
遺族にとっても、故人を思い出す良い機会となり、思い出話を通じてその人の存在を再確認できるでしょう。
このように、故人の記憶を共有することは、形見分けの意義をより一層深めてくれます。
④法事に参加する
形見分けを受けた後、法事に参加することもお礼の一つの方法です。
遺族が故人を偲ぶための大切な場に参加することで、故人への敬意を直接表現できるからです。
参加する際は、礼儀をわきまえた服装や態度を心がけ、遺族や他の参列者に配慮することが大切です。
法事の場は故人との思い出を共有し、感謝の気持ちを再確認する絶好の機会となるため、選択肢の一つとして検討してみましょう。
⑤カタログギフトを贈る
感謝の気持ちを表現する手段として、カタログギフトを贈る方法もあります。
カタログギフトは相手の好みに合わせた選択肢を提供できるため、遺族にとっても喜んでいただける贈り物になるでしょう。
ただし、形見分けをする側、形見をもらう側の双方にとって気を遣う形になりかねませんので、互いの関係性や状況をうまく把握したうえで行うことをおすすめします。
形見が不要になった場合の3つの対処法
「もらった形見が不要になった時はどうすればいいの?」という疑問をお持ちの方もいるででしょう。
そんなときは、以下の3つの方法で処分しましょう。
- お焚き上げする
- 寄付・寄贈する
- 売却する
いずれの方法を選んだとしても、形見の扱いには慎重さと感謝の気持ちが求められます。
不要になったときに備えて、すべて押さえておきましょう。
①お焚き上げする
形見が不要になった場合には、お焚き上げという手段を検討しましょう。
お焚き上げは、遺品を焚き上げることで故人の魂を天へ送り、供養の意を込めた大切な儀式です。この行為は、特に故人にとって重要だった品物や思い出深いものに敬意を示す方法として広く認識されています。
お焚き上げを実施する際は、神社や寺院に依頼するのが一般的で、専門の知識を持つ業者に任せる方法もあります。さらに、一部地域では地域の行事としてお焚き上げが行われており、そのような場に参加すると地域の習慣に従った形で供養ができる機会ともなります。
このように、お焚き上げは形見や遺品を尊重しながらしっかりと供養する意味深い方法といえるでしょう。

②寄付・寄贈する
受け取った形見が不要になった場合には、寄付や寄贈を検討することも有意義な選択肢です。
まだ使える衣類や家具、書籍などを福祉施設や慈善団体に寄付することで、多くの人々に喜んでもらえるだけでなく、形見を通じて供養の思いを形にすることができます。
この行為は、故人の大切な思い出を生かし、他者への貢献へとつなげられるため、非常に意義深いものとなるでしょう。また、特定の趣味やコレクションについては、同じ興味を持つ人々や研究機関に寄贈することで、故人の愛した物が新たな価値を見つける可能性もあります。
同じ志を持つ人々に大切に受け継がれることは、心のこもった供養となり、故人への敬意を示す一つの方法と言えるでしょう。

③売却する
形見を売却することも一つの選択肢として考えられます。
ただし、特に高価な品物や希少価値のあるものの場合、適正な価値を理解した上での売却が重要です。信頼できる買取業者やオークションを利用することで、適切な価格で手放すことができます。
また、必要に応じて鑑定に出す方法も検討しましょう。特にコレクションについては価値が高い場合もあるからです。
売却を通じて得た資金を故人の好きだった活動や、慈善事業に寄付することも、供養の一環として大切な行動です。こうすることで、故人の思いを生かしながら、バランスの取れた対処が可能となるでしょう。

まとめ
今回は形見分けでのお返しの必要性について解説しました。
形見分けは、故人を偲びながら遺族や大切な人々と思い出を共有する貴重な行為です。形見分けには、相手への敬意と配慮が重要であり、基本的にはお返しが不要である点も大切な特徴です。
お返ししなくていい理由としては、以下の3つがあります。
- 形見はお祝いの品やプレゼントではないから
- そもそも遺族は求めていないから
- お返しが慣習となっていないから
形見を受け取ることに戸惑いや負担を感じても、お返しは強制ではありませんので、感謝の気持ちをもって受け入れるようにしましょう。
また、形見が不要になった場合の対応として、以下のような選択肢も押さえておきましょう。
- お焚き上げする
- 寄付・寄贈する
- 売却する
どの方法を選ぶにせよ、故人への感謝と思いを忘れずに対応することが大切です。
形見分けをより意義深いものにするためにも、知識やマナーをしっかり理解し、実践してみてくださいね。