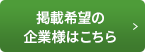遺品整理はいつから始めるのがベスト?―遺品整理をするポイントも解説―
2023.12.08

- 遺品整理はいつから始めるべき?
- 遺品整理の流れやコツが知りたい
- 遺品整理で気をつけることは?
こんな悩みにお答えします。
ご両親や身近な人との別れは悲しみが深く、なかなか遺品の整理に手をつけられない方も多いのではないでしょうか。
故人の遺品を見ると、懐かしい日々が思い出されたり、募る想いもたくさんあるでしょう。
しかし、いつまでも遺品整理をしないと思わぬ費用やトラブルが発生しますので、遺品整理は計画的に進める必要があります。
本記事でわかることは次のとおりです。
- 遺品整理を始めるときに目安となる5つのタイミング
- 遺品整理が遅くなると発生する5つのリスクと注意点
- 遺品整理をスムーズに進める3つのコツ
「遺品整理をいつから始めるべきか?」に正解はありません。
だからこそ本記事を最後まで読むことで、適切な遺品整理のタイミングがわかり、計画的にスムーズな遺品整理ができますので、ぜひ参考にしてください。
遺品整理はいつからするべき?目安となる5つのタイミング
結論、遺品整理を始める時期に決まりはありません。
なぜなら、あなたや親族の気持ちに整理がついたタイミングこそが、適切なタイミングだからです。
とはいえ、「それじゃなかなか遺品に手をつけられないし、漠然と年月が過ぎるばかりだよ」と思われる方もいるでしょうから、目安となるタイミングを5つご紹介します。
- 葬儀後すぐ
- 諸手続きが終わった後
- 四十九日を迎えた後
- 相続税の発生前
- 親族が集まるタイミング
これらを参考にして、遺品整理のタイミングを決めましょう。
ただし、遺品整理は1人で始めるのではなく、必ず親族で話し合ってから進めてください。
相続人などの親族を集めずに遺品整理をすると、後々のトラブルの元になるからです。
①葬儀後すぐ
葬儀後すぐの遺品整理は、次のようなケースで多く検討されます。
- 親族が遠方に住んでいる
- 故人が賃貸物件や介護施設で生活していた
- 故人の借りている部屋の清掃が必要
いずれも時間的、金銭的に急いだほうが良いからです。
親族が遠くにいると集まる機会が少なく、スムーズに遺品整理を進めにくいので、葬儀後や告別式と並行して遺品整理を始めることが多いです。
故人が賃貸住宅に住んでいた場合は、2週間から1ヶ月で解約して退去する必要がありますので、早く遺品整理に着手しないと家賃がどんどんかかってしまいます。
また、孤独死や孤立死した場合、死因によっては血液などの体液や悪臭を清掃する必要があります。特殊清掃を行う業者や遺品整理業者に依頼するなど、なるべく早い段階から遺品整理を始めなければなりません。
関連記事:遺品整理を49日前からしても問題ない理由(実は故人にメリットあり)
②諸手続きが終わった後
諸手続が終わったタイミングとは、
- 死亡届の提出
- 健康保険証などの返納
- 水道・ガス・電気などの契約解除や変更
など、優先的にする必要がある手続きがひと段落したタイミングを指します。
先に必要な手続きを終わらせれば、相続財産など遺産分割協議で必要な情報を事前に整えたうえで親族間で話し合えるからです。
遺品整理を始めたものの、次々に必要な手続きが出てくるようではスムーズに進められませんので、諸手続きを先に終わらせてからの遺産整理も視野に入れましょう。
③四十九日を迎えた後
遺品整理を始めるのが多いと言われるのが、四十九日(しじゅうくにち)を迎えた後のタイミングです。
仏教では、故人が亡くなってから49日間は魂が現世を彷徨っていると考えられており、魂が現世から離れるのが四十九日を迎えた後のタイミングだからです。
四十九日の法事は親族が集まる機会ですので、話し合いをしやすく、遺品整理をする時期として向いているでしょう。
④相続税の発生前
相続税を申告するまでには遺品整理を始めましょう。
なぜなら、相続税は相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければならず、納税が遅れると追徴課税が課されるからです。
相続税の非課税枠を超える相続財産は、すべて課税の対象です。
遺産分割協議にゆとりを持つべく、相続税の申告期限までには計画的に遺品整理を始めましょう。
⑤親族が集まるタイミング
四十九日以外にも、
- 百箇日法要
- 一周忌
- 三回忌
などの親族が集まる機会も遺品整理を始めるには良いでしょう。
賃貸契約などの金銭的な負担を考える必要がなく、相続税の申告など必要な手続きが終わっていれば、一回忌や三回忌という時間が経ったタイミングも、集まった親族で丁寧に遺品を整理できる機会となります。
時間にゆとりがあるケースに向いているでしょう。

遺品整理が遅れると発生する5つのリスクと注意点【後悔する前に】
遺品整理を始めるタイミングはさまざまだとお伝えしましたが、遺品整理が遅れると以下のようなリスクに見舞われる可能性があります。
- 相続税が多くかかる
- 相続放棄ができなくなる
- 固定資産税や家賃、保険料が多くかかる
- トラブルに巻き込まれるリスクが上がる
- 月額・年額料金がかかり続ける
必要のない出費を避けるためにも、必ず確認しておきましょう。
相続税が多くかかる
遺品整理が遅くなり、相続財産などの把握が遅れて相続税の納税期限を過ぎてしまうと、追徴課税の対象になりますのでご注意ください。
相続税は死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければならないからです。
追徴される税金の種類は下表のとおりです。
| 追徴課税の種類 | 内容 |
|---|---|
|
無申告加算税 (期限内に申告をしなかったとき) |
・期限後に自主的に申告した場合、納税する金額の5%が追徴される ・税務調査によって相続税の無申告が判明した場合、納税する金額の15%が追徴される ・追加で納税する金額が50万円以上の場合、超えた部分に対して20%が追徴される |
|
過少申告加算税 (本来納める金額より少なく申告したとき) |
・追加で納税する金額の10%が追徴される ・追加で納税する金額のうち、当初申告した金額もしくは50万円のうち大きい方の金額を超えた場合、超えた部分に対して15%が追徴される ※これらは税務署に指摘される前に修正申告した場合にはかからない |
|
重加算税 (偽ったり隠蔽したり、悪質な申告だと判断されたとき) |
・追加で納税する金額の35%が追徴される |
|
延滞税 (納税期限を過ぎたとき) |
・納税期限の翌日から納税した日までの日数に応じて、利息に相当する金額が追徴される ・相続税の申告を意図的にしていなかったとみなされると、追加で納税した金額の40%が追徴される |
延滞税は納税期限を過ぎると必ずかかります。
たとえば、納税する金額は正しくても納税期限を過ぎてしまった場合は、無申告加算税と延滞税の両方が課税されます。
なお、相続財産はわかりやすい金銭以外にも、以下のような金銭的価値を持つ遺品も課税対象です。
- 貴金属
- 美術品
- 骨董品
遺言書が出てきたり、借金などのマイナスの財産が出てきたりする可能性を考え、早めに遺品整理をして把握しておきましょう。
相続放棄ができなくなる
遺品整理が遅れると、相続放棄のタイミングを逃して多額の負債を抱えるリスクがあります。
相続ではマイナスの財産も対象になりますが、相続放棄ができるタイミングを逃した後にマイナスの財産が発覚すれば、マイナスの財産を引き継がざるを得なくなります。
故人に多額の借金などがある場合は、深刻なケースに発展するでしょう。
相続放棄する場合は、あなたが故人の相続人であると知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所にて所定の手続きをする必要があります。何もしないで3ヶ月を過ぎてしまうと、相続を承認したと判断されますのでご注意ください。
また、相続放棄する場合は、遺品に手をつけないようにしましょう。
相続するとみなされるおそれがあるからです。
相続放棄の申告期限が過ぎてしまっても、諦めずに冷静に対応しましょう。
中には家庭裁判所に申し立てて放棄が認められたケースもあります。
固定資産税や家賃、保険料が多くかかる
遺品整理が遅れて故人の住居の処理が遅くなれば、以下の費用が継続的にかかる点にご注意ください。
- 固定資産税
- 賃貸料
- 火災保険料
適切に対応しない限り継続的な負担になりますので、早めに対策しましょう。
固定資産税は相続人が納税義務を負う
固定資産税は1月1日時点の土地・建物の所有者に納税義務がありますが、所有者が死亡している場合は相続人が引き継ぐことになります。
故人の家を手放すのであれば早いに越したことはありませんし、相続する場合は3ヶ月以内に不動産登記簿の名義を変更しましょう。
「特定空き家」は固定資産税が高くなる
2015年に施行された「空き家対策特別措置法」に基づき、「特定空き家」に認定されると固定資産税が高くなります。
特定空き家とは、次の条件に該当する空き家です。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
認定されるの流れは以下のとおりです。
- 空家調査により特定空き家に認定
- 助言・指導される
- 勧告される(固定資産税の軽減措置が適用されなくなり固定資産税が増える)
- 改善命令(命令違反すると50万円以下の罰金が課される)
- 行政代執行により解体される(所有者に対して解体費用が請求される)
解体まで至ると罰金に加えて、何百万円もかかる解体費用まで請求されますので、早期に対処しましょう。
賃貸料がかかり続ける
アパート・マンションに住んでいた場合、賃貸契約は死亡と同時に消滅しません。
契約の効力は続きますので、相続人が賃貸人の地位を引き継ぐことになります。
不要な出費を減らすためにも、早期に対処しましょう。
トラブルに巻き込まれるリスクが上がる
空き家を放置すればさまざまなリスクに見舞われることを覚えておきましょう。
自然発火による火災のリスク
水道、ガス、電気は早めに手続きをして停止しましょう。
たとえば、コンセントにホコリが溜まって発火するなど、人が住まなくなると火災のリスクはグッと高まるからです。
相続人が損害賠償責任を負うことになりますので、ご注意ください。
犯罪の拠点になるリスク
空き家で放置すると、以下のような犯罪の拠点となるリスクが高まります。
- 空き巣による盗難
- 不法占拠
- ゴミの不法投棄
- 放火
- 違法薬物の栽培
勝手に捨てられたゴミが環境汚染につながったり、捨てられた生ゴミをエサに害虫や害獣が集まったり、隣人の迷惑になりトラブルに発展するケースも考えられます。
空き家にしておく間はきちんと施錠し、しっかり雨戸も閉め、定期的に訪れて犯罪の温床にならないように管理しましょう。
空き家の倒壊リスク
空き家は人が住んでいる家よりも傷みやすく、以下のような老朽化が進みやすい状態です。
- 木材や金属が腐食
- 外壁や屋根などの劣化・破損
- シロアリ被害
台風や大雨などの自然災害により、知らない間にどんどん傷んでいることも。
家屋が倒壊すれば隣家や通行人に大きな被害を与えてしまい、その責任は所有者である相続人が負います。
損害賠償責任を負うリスクが高まりますので、空き家は定期的に老朽化の進行を確認しましょう。
月額・年額料金がかかり続ける
家賃と同じく、サブスクリプションのような月額・年額で費用がかかるサービスは早めに停止しましょう。
継続的に費用がかかるだけでなく、放置すれば不正利用されるリスクや、アカウントの乗っ取りリスクも発生するからです。
アカウント内には個人的なデータや重要データが残っている可能性もありますので、適切なデータ保管や遺族への引き継ぎを行いつつ、更新日を確認して早めにサービスの利用を停止をしましょう。

遺品整理をスムーズに進める3つのコツ
遺品整理をスムーズに進めるために、次の3つのコツを押さえておきましょう。
- 遺品整理までに必要なことを済ませる
- スケジュールを決める
- 遺品を4つに仕分けて整理・処分する
では、順番に解説します。
遺品整理までに必要なことを済ませる
故人にまつわる以下の手続きを先に済ませておきましょう。
- 死亡届の提出
- 葬儀
- 健康保険証などの返納
- 年金受給者死亡届の提出
- 世帯主の変更届
- 水道・ガス・電気などの公共料金の解約
- 携帯電話や各種サブスクリプションの解約
- 保険の変更手続きや解約
これらの必要な手続きを先に済ませておけば、遺品整理に集中できるからです。
手続きを通じて遺産分割協議で必要な情報も見つけられるメリットがあります。
スケジュールを決める
遺品整理は漠然と進めるのではなく、計画的に進めましょう。
故人との思い出に浸ったり、悲しみに襲われたり、予想外の出来事が発生しやすいからです。
まずは遺品整理に必要な、以下のような人が集まれる日を決めます。
- 遺品整理に携わるべき親族
- 相続権者
- 不用品を処分するために車を手配する人 など
次に、遺品整理を終わらせる日を決めます。
そして、次のような段取りを決めながら遺品整理をします。
- リビングから片付ける
- 書類を中心に整理する
- 残すものと処分するものを仕分ける など
スケジュールには余裕を持って、計画的に遺品整理を進めましょう。
遺品を4つに仕分けて整理・処分する
遺品を次の4つに分けると、整理しやすくなります。
- 貴重品
- 思い出の品(形見)
- 再利用できるもの
- 廃棄するもの
処分を迷うものは保留にして進めましょう。
たとえば、
- 写真
- 日記
- 手紙
- 住んでいたアパートの風景
のような思い切って捨てられない物や、物理的に残せない物は、写真や動画などのデータとして残しておきましょう。
関連記事:〖簡単4ステップ〗アルバム・写真を遺品整理する方法(すっきり片付けられる)
貴重品
貴重品とは以下のようなものです。
- 銀行の通帳やキャッシュカード
- クレジットカード
- 有価証券(株式、債券、小切手、手形など)
- 不動産などの権利関係書類
- 各種の契約書類
- 宝飾品や美術品・骨董品などの価値のあるもの
- 金庫と金庫の鍵
- 身分証明書など(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、年金手帳)
- 印鑑登録した実印
- 切手
- コインなどの価値あるコレクション品
- 公共料金などの請求書
前述しましたが、相続や手続きに必要な重要書類を優先的に探しましょう。手続きには期限がありますので、早急に対応する必要があります。
エンディングノートや遺言書がある場合は、内容を確認し、指示に従って遺品整理を進めましょう。親族間のトラブル回避にもつながります。
自筆の遺言書がなくても、公証役場にて交渉証書遺言があるかどうかも確認しておきましょう。
思い出の品(形見)
故人が愛用していたものや、思い出のある次のような品です。
- 写真
- 日記
- 手紙
故人との思い出を大切に保管するためにも、誤って処分しないように明確に分けておきましょう。
再利用できるもの
次のような再利用できるものは、ルールに従って適切に処分しましょう。
- 家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機)
- その他の家電(携帯電話、タブレット端末、パソコンなど)
- 家具(ベッド、ソファ、タンス、テーブル、イスなど)
- 衣類
- 金属類
適当に廃棄すると、法律に違反することもありますのでご注意ください。
- 再利用するために保管しておく
- 自治体の回収サービスを使う
- 遺品整理業者や不用品回収業者に依頼する
- リサイクル業者に引き取ってもらう
- 買取専門店に売る
- 家電量販店に引き取りを依頼する
など、処分したいものによって処分方法は異なります。
まずは自治体のホームページで確認しましょう。
廃棄するもの
遺品整理で出るゴミの種類は主に次の4種類です。自治体のルールに従って処分しましょう。
【燃えるゴミ(可燃ゴミ)】
- 生ゴミなどの台所ゴミ
- 木質ゴミ
- 衣類・布類
- 皮革類
- ゴム製品
- ビニール製品
- リサイクルできないプラスチック製品 など
【燃えないゴミ(不燃ゴミ)】
- 陶磁器類
- ガラス類
- 金属類
【資源ゴミ(再資源化が可能なゴミ)】
- 新聞・雑誌・ダンボールなどの古紙
- かん
- びん
- ペットボトル
【粗大ゴミ】
- 大型家具
- 大型家電(家電4品目を除く)
- 大きな布類
- 自転車
- ベッド・マットレス・カーペット など
関連記事:〖2分でわかる〗遺品整理で出るゴミを処分する3つの方法(もう迷わない)

【抱え込む前に】遺品整理業者への依頼もおすすめ
「自分たちではとても片付かない。どうしたらいいの?」と悩む方もいるでしょう。
以下のような場合、遺品整理業者への依頼を検討しましょう。
- 時間に限りがある
- 自身の体が不自由で遺品整理ができない
- 遺品が多くて残された家族では対応できない
- 孤独死などで、遺体の状態より特殊清掃が必要
遺品整理業者に依頼すれば、遺品の整理・処分をすべて任せられるので、手間と時間をかけずに遺品整理ができます。
業者によって料金体系やサービス内容に違いがありますので、口コミやネット上での評価などを参考にしつつ選びましょう。
追加料金を請求されないように、必ず事前に見積もりを取り、追加料金が発生するケースについても確認しておきましょう。
遺品整理業者に依頼するメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
・手間と時間がかからない
・気持ちの面で整理がつきやすく、肉体的にも疲れない
・貴重品の捜索に長けている
・遺品の供養を任せられる
・特殊清掃を任せられる
・不用品を回収してもらえる
・不用品を買い取りしてもらえると、費用を抑えられる
|
・費用がかかる
・残された家族のペースで遺品整理できない
|
費用は数万円から数十万円かかりますので、最大のデメリットになるでしょう。
とはいえ、故人の遺体の状態によって必要になる、体液などの汚れや悪臭の特殊清掃を任せられ、遺品の供養など親族に寄り添ったサービスが期待できるのは大きなメリットです。
自分たちで抱え込んで悩む前に、遺品整理業者の検討も視野に入れつつ、遺品整理を進めましょう。
遺品整理はいつからでもOK!思わぬ出費や親族間トラブルにご注意を
今回は遺品整理のタイミングと、遺品整理にまつわる注意点やコツについて解説しました。
本記事をまとめると、
- 「遺品整理をいつから始めるか?」に正解はなく、適切なのは親族の気持ちに整理がついたタイミング
- 一般的には四十九日を迎えた後のタイミングが多い
- とはいえ、遺品整理が遅れると相続税の申告が遅れたり、家賃や保険料など月額・年額でかかる費用が継続するので、状況によっては早めの着手がおすすめ
- 親族間のトラブルを避けるためにも、1人で勝手に遺品整理を進めないこと
- 遺品整理は計画的にルールを決めると進めやすいが、親族だけで対応できない場合や事情によっては遺品整理業者への依頼がおすすめ
遺品整理をいつから始めるかは自由に決められる一方で、故人や残された親族の状況によってさまざまです。
いつまでも遺品整理をしないと数々のリスクに見舞われますので、本記事を参考に計画的な遺品整理を進めていきましょう。