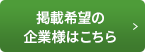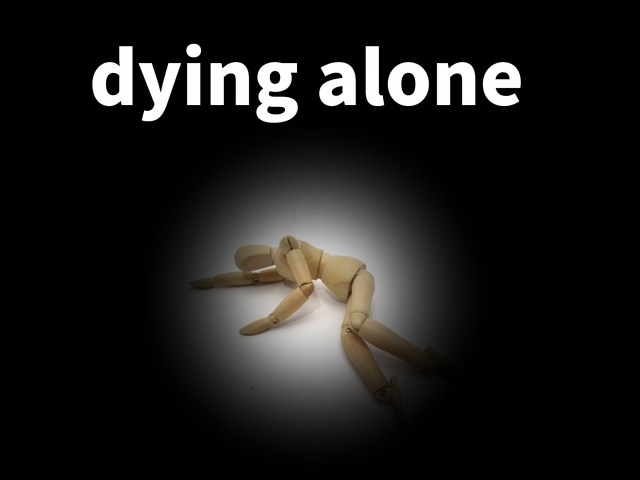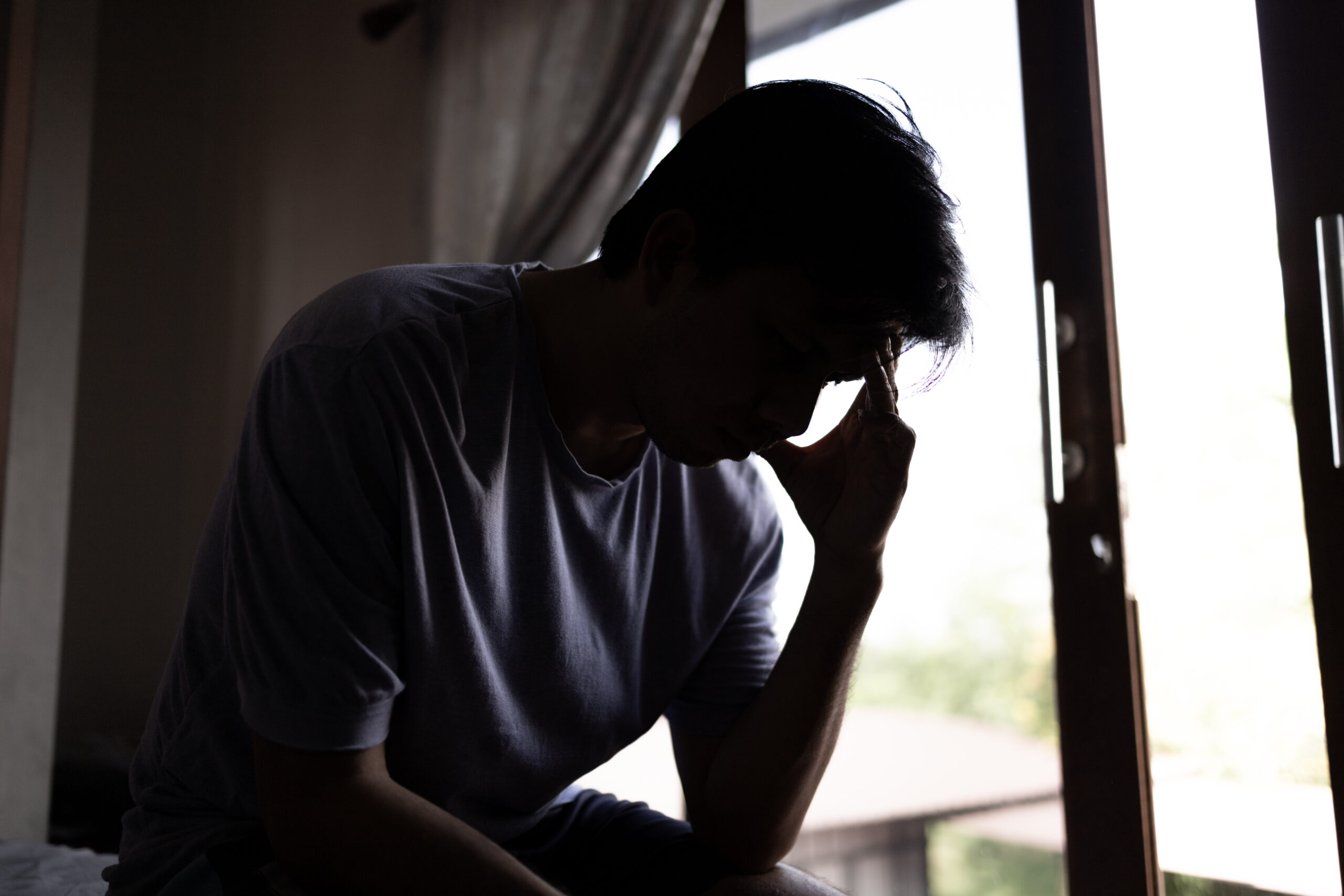【完全ガイド】一人暮らしの人が亡くなったら?死亡後の手続きの流れを徹底解説!
2025.05.15

- 一人暮らしで亡くなった場合、どんな手続きが必要かわからない
- 身寄りが少なく誰に相談すべきかわからない
- 遺品整理や家の処分にどのくらいの手間がかかるか不安
こんな悩みにお答えします。
一人暮らしで亡くなった場合、残された家族や関係者は多くの煩雑な手続きを行う必要があります。不安や戸惑いを抱える方も多いですが、必要なステップを事前に知っておくことで、冷静に対応できます。
この記事でわかることは、以下のとおりです。
- 一人暮らしの人が亡くなったら行う5つの『公的』手続き
- 一人暮らしの人が亡くなった際の『相続関係』の手続き
- 一人暮らしの人が亡くなった際の『税金関係』の手続き
- 忘れがちな死亡に関するその他の手続き
- 生前に死亡後の手続きを対策する方法
この記事を読めば、一人暮らしの方が亡くなった際にどのような準備や行動を取ればよいのかが具体的にわかります。
もしもの時に備えて理解しておくことで心の負担を軽減できますので、ぜひチェックしてみてください。

一人暮らしの人が亡くなったら行う5つの公的手続きとは?
一人暮らしの人が亡くなった場合、いくつかの公的手続きを速やかに行う必要があります。
具体的には、以下の5つです。
- ①死亡届を提出する
- ②葬儀や火葬を手配する
- ③資格喪失手続きをする(年金・健康保険など)
- ④各種契約を解除・清算する
- ⑤遺品整理をする
それぞれ順に解説します。
①死亡届を提出する
死亡届は、亡くなった方の死亡を正式に記録するために必要な手続きです。
医師が死亡診断書を発行した後、7日以内に本籍地または死亡地の市役所に提出します。
この届出を行うことにより、火葬許可証が発行され、以後の葬儀の準備がスムーズに進むこととなります。
提出する際、届け出る人の情報や、故人の関係性についても必要になるため、しっかりと確認しておくことがが求められます。
②葬儀や火葬を手配する
死亡届を提出後、葬儀や火葬の手配に入ります。
故人の意思や希望を考慮しながら、葬儀社と契約することが一般的です。多くの場合、葬儀は亡くなってから24時間後に行いますが、地域や宗教によって異なる点もあります。
故人が残した希望を尊重し、親族や友人に連絡を取り、葬儀参加者の調整も行う必要があります。
もし親族がいない場合、自治体によって火葬されます。
③資格喪失手続きをする(年金・健康保険など)
亡くなった方が受給していた年金や健康保険について、資格喪失手続きを進めます。
年金受給者であった場合、「年金受給権者死亡届」を提出し、年金の給付を停止します。また、健康保険や国民健康保険の場合、資格喪失届を提出し、保険証を返却します。
これらの手続きは亡くなってから14日以内に行うことが求められているため、早めの対応が必要となります。
④各種契約を解除・清算する
故人が契約していた賃貸契約や公共料金、携帯電話などの解約手続きも欠かせません。
手続きは早めに行うことで無駄な費用を回避できます。特に賃貸契約の場合、速やかな部屋の明け渡しが求められます。
また、故人が保持していたクレジットカードや会員契約なども点検し、必要な解約手続きを進めていくことが求められます。
これらを怠ると支払い料金がかさんだり、損害賠償金を求められたりするなど、トラブルになる恐れがあるため注意しなければなりません。
⑤遺品整理をする
遺品整理は、一人暮らしの故人が使用していた家具や日用品、思い出の品などを整理する作業です。
この作業は感情的にも大変であり、作業には多くの時間や労力を要することが一般的です。特に賃貸住宅での遺品整理では、家の契約解除や退去期限が関わるため、迅速かつ計画的な対応が求められます。
ただし、故人が使っていた家具や家に関する物品の中には、思いがけず価値のあるものが含まれることもあるため、むやみに処分してしまわないように注意しなければなりません。特に価値のある遺品については、相続財産と見なされる場合があるため、慎重な判断が必要です。
相続人がいない場合や対応が難しい場合には、専門の相続財産清算人を選任して整理を進める方法もあります。
一人暮らしの人が亡くなった際の相続関係の手続きとは?
一人暮らしの方が亡くなった場合、公的な手続きはもちろん、相続関係の手続きも必要になります。
まず重要なのは、故人の遺産をどのように扱うかを明確にすることです。
なぜなら、相続手続きは通常、相続人が行うことが基本ですが、相続人が不在の場合や認知症などの場合は手続きが複雑化するケースが多々あるからです。
ここでは一般的な相続関係の手続きの流れについて、説明していきます。
まずは遺言書を探す
相続関係の手続きを進めるにあたって、まず最初に行うべきことは、故人が遺言書を残しているかどうかの確認です。
遺言書が見つかった場合、その内容に基づいて家やその他の遺産の分配を比較的スムーズに進められるからです。
遺言書には大きく分けて公正証書遺言と自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。特に公正証書遺言は法律的な効力が強く、遺産分割におけるトラブルを未然に防ぐためにも重要視されています。
遺言書を保管している可能性のある場所を探し、分からない場合は家族や知人に尋ねることが有効です。また、場合によっては弁護士や司法書士といった専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることも役立ちます。
遺産を分割する
遺言書を探して遺産の取り扱いが明確になった場合は、遺産の分割に進みます。
遺言書の記載内容に従うことが重要ですが、もし遺言書が存在しない場合、法定相続分に基づいて相続人同士で話し合いを行います。
この際、相続人の数や関係性、さらに遺産の中に家や土地が含まれるかどうかなどによって分配方法が異なるため、細かな確認が求められます。また、家屋などの不動産は評価額の算出や実際の利用状況などを考慮する必要も出てくるため、専門家の意見を参考にすることも有効です。
次項で深掘りしますが、相続税の申告を忘れないよう注意することも大事です。相続税の申告には期限が定められているため、計画的なスケジュール管理を徹底することが肝心となります。
一人暮らしの人が亡くなった際の税金関係の手続きとは?
一人暮らしの人が死亡した場合、故人の財産や税金に関する手続きを正確かつ迅速に行う必要があります。
相続税は故人が所有していた財産の総額を基に計算され、相続人が法定相続分に応じて負担します。なお、相続税には基礎控除が設けられているため、この控除額を超える財産がある場合に申告が求められます。
また、相続税の納付は期限が決まっているため、早めに行動することが重要です。もしも納付に遅れた場合は延滞税など、余計な税負担がのしかかることとなります。
ですので、一人暮らしの方が亡くなった際には、相続人が手続きを円滑に進められるよう、必要書類の準備や遺産の調査などを早く行わなければなりません。
相続税を申告・納税する
相続税の申告は、被相続人が死亡した日から10ヶ月以内に行う必要があります。
相続税の手続きを進める際には、相続する財産の評価額や相続人の情報を正確に書いた申告書に加え、必要書類を必ず添付することが求められます。
具体的な書類としては、遺産明細書や不動産の評価証明書などです。これらの書類を適切に準備し、申告手続きを正確に進めなければなりません。これを怠ると後々問題が発生し、手続きが複雑化する可能性があるからです。
また、納税期限を逃さないようにするため、計画的なスケジュール管理も必要です。相続税に関する手続きは、時間と労力がかかる場合があるため、余裕をもって準備を進める必要があります。
準確定申告を行う
亡くなった方が所得を得ていた場合には、準確定申告を行う必要があります。
これは、故人が亡くなられた年の1月1日から死亡した日までの所得に関する申告手続きであり、期限は死亡日から4ヶ月以内と定められています。
この申告により、未納となっている税金の清算が行われ、必要に応じて還付を受けることも可能です。
準確定申告を進める際には、遺族が故人の所得を正確に把握し、必要な関連書類を準備することが求められます。

忘れがちな死亡に関するその他の手続き
一人暮らしの方が亡くなると、多くの手続きが必要になります。
特に忘れがちな手続きは、以下のとおりです。
- 生命保険金などの受け取り
- 運転免許証の返納手続き
- クレジットカードの利用停止手続き
- 携帯電話契約の解約
これらの手続きを怠ると、後々のトラブルや不便につながる可能性があります。一人暮らしの方が亡くなった際に、残された家族を困らせないためには、事前に情報を整理しておくことが何より重要です。
ぞれぞれ事前に確認しておきましょう。
生命保険金などの受け取り
故人が加入していた生命保険に関しては、保険金の受け取り手続きを行う必要があります。
保険会社に連絡し、必要な書類を提出することで手続きが進められます。
保険会社によって異なる点はありますが、具体的には以下のような書類が求められます。
- 死亡証明書
- 保険証券
- 受取人の身分証明書
- 戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 委任状 など
残された家族はこれらの書類を揃えたうえで、保険金を請求することになります。
運転免許証の返納手続き
故人が運転免許証を保持していた場合、その返納手続きも忘れずに行う必要があります。
返納は運転免許試験場や警察署で行えます。必要な書類としては、故人の運転免許証と死亡証明書が求められます。
この手続きを行わずにいると、免許証の不正利用につながる可能性があるため注意が必要です。
クレジットカードの利用停止手続き
亡くなった方が保持していたクレジットカードについても、速やかに利用停止手続きを行います。
クレジットカード会社に連絡し、死亡証明書を提出することで利用停止できます。
手続きを怠っていると、故人の名義で利用されるリスクがあり、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
携帯電話契約の解約
携帯電話契約も忘れがちな手続きの一つです。
携帯電話会社に連絡し、契約者の死亡を伝えることで解約手続きを進めます。この際、多くの場合で故人の死亡証明書が必要となります。
契約の解約を忘れると月々の利用料金が発生し続け、親族に請求が来るリスクがあるため、忘れずに早期に解約する必要があります。
死亡の事実はすみやかに知らせよう!
一人暮らしの方が亡くなった場合、死亡の事実を速やかに周囲に知らせることが重要です。
なぜなら、遺族や友人に対する通知が遅れると、故人の意に反して手続きが進んでしまうリスクがあるからです。
死亡の事実を知ったときは、迅速な対応が求められます。
死亡の際の関係者への連絡手順
まず、死亡を確認した医師から死亡診断書をもらったら、直ちに関係者への連絡に取りかかりましょう。
子どもや配偶者、兄弟姉妹といった近い親族には優先的に報告し、その後、故人の友人や知人へも通知します。特に親族は、葬儀に参加できるかどうかの確認も必要になるため、すぐに連絡を入れておくと時間的な余裕が生まれます。
さらに、連絡を入れる時は故人の状況や亡くなった理由について、配慮した言葉を選ぶことが求められます。一方的に事実を伝えるのではなく、相手の反応にも気を配ることが大切です。
連絡の際には、葬儀の日程や場所も合わせて伝えておくと、後の手続きがスムーズになるでしょう。
訃報の通知と葬儀参加者への案内
訃報の通知が済んだら、次は葬儀の案内を整えます。
故人の葬儀についての詳細、日時、場所、形式などは、できるだけ早く周知することが必要です。葬儀社には、連絡をした親族や友人に情報を送ってもらうことも一つの選択肢となります。
費用の捻出や式の選定などにも取り組む必要があるため、参加者の数を把握することで、より適切な準備が整います。
故人を悼む気持ちを大切にしながら、その日を迎えられるよう心がけることが重要です。
生前に死亡後の手続きは対策できる!
一人暮らしの方が亡くなった際の手続きをスムーズにするためには、事前に対策を講じることが重要です。
生前にしっかりと準備をしておくことで、遺族や親しい人に余計な負担をかけることなく、自分の希望に沿った形で手続きを進めることが可能です。
具体的には、死後事務委任契約や遺言書の作成が考えられます。
それぞれくわしく解説します。
死後事務委任契約をしておく
死後事務委任契約は、生前に信頼できる人や専門家に、自分が亡くなった後の手続きを委任するための契約です。
この契約を結ぶことで、死亡届の提出、葬儀や火葬の手配、遺品整理、公共料金や契約サービスの解約手続きなど、煩雑な事務作業を任せることが可能になります。
特に、一人暮らしで亡くなった場合、家族などがすぐに対応できないケースも想定されるため、このような準備が重要です。
一人暮らしで亡くなった場合には特に、有事の際に迅速な対応が期待できるため、死後事務委任契約は安心感を高める大きなサポートとなります。また、この契約によって、自分の望む葬送方法や遺品整理の進め方を実現することも可能となり、将来のさまざまな不安の軽減につながります。
遺言書を作成しておく
遺言書を作成することも極めて重要な手続きです。
遺言書には、自分の財産の分配や、特定の人に贈与したいもの、葬儀の形態に関する希望などを明記できるからです。特に財産の相続については、遺言書があることによってトラブルを避けられることが多いです。
遺言書は公正証書遺言として作成することで、法的効力が高まり、意向が尊重される可能性が高まります。
また、生前に遺言書の内容を家族や親しい人に伝えておくことも、後の混乱を防ぐ助けとなります。法的拘束力はありませんが、自分の考えを残しておけるため、エンディングノートを作成するのも有効です。

まとめ
今回は一人暮らしの人が亡くなったら必要になる手続きについて解説しました。
以下のような手続きは、死亡後には速やかに手続きを進める必要があるため、迅速かつ正確に行うことが重要です。
- ①死亡届を提出する
- ②葬儀や火葬を手配する
- ③資格喪失手続きをする(年金・健康保険など)
- ④各種契約を解除・清算する
- ⑤遺品整理をする
また、相続税や準確定申告には申請期限が設けられているため、一人暮らしの人が亡くなった後は、速やかに遺言書を確認し、遺産分割協議や故人の所得の把握を進める必要があります。
以下のような手続きも忘れることなく、進めるようにしましょう。
- 生命保険金などの受け取り
- 運転免許証の返納手続き
- クレジットカードの利用停止手続き
- 携帯電話契約の解約
一人暮らしの方にとっては生前対策をしておけば、さらなる安心感を得られます。たとえば、死後事務委任契約や遺言書の作成がが効果的です。
これらの対策は、遺族や親しい人が迷わず手続きを進める助けとなり、無駄なトラブルを防ぐ効果も期待できます。
死亡後の手続きは決して他人事ではありません。必要に応じて、あらかじめ信頼できる専門家と相談し、必要な情報を整理しておくと、いざというときに冷静に対処できます。
準備を進めることは、大切な人への思いやりを形にする第一歩です。この機会にもしもの時に備えて理解を深めておきましょう。